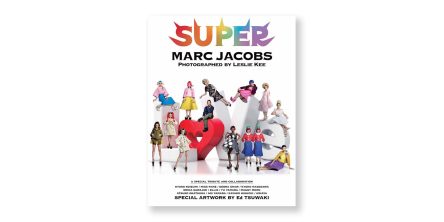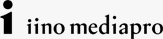広告や雑誌で描かれる“ビューティ”は、ただ美しいだけでなく、その時代の背景や文化を映しとる鏡でもある。
コロナ禍にある2021年。今の時代に表現していくべきビューティ、美しさとは何か? クリエイティブディレクター、ブランディング・コンポーザー、メイクアップアーティスト、フォトグラファー、それぞれの立場から語っていただく。
座談会メンバー: (上写真右から)
UDA(メイクアップアーティスト)
東浦真弓(ブランディング・コンポーザー)
小野 健(資生堂 クリエイティブ本部 エグゼクティブ・クリエイティブディレクター)
ND CHOW/アンディ・チャオ(フォトグラファー)
モデレーター:坂田大作(SHOOTING編集長)
坂田:ではUDAさんから簡単に自己紹介をお願いします。
UDA:メイクアップアーティストのUDAです。エディトリアルからファッションやビューティの広告とか、CMやショーなどで仕事をさせて頂いています。
最近、本を出しました!
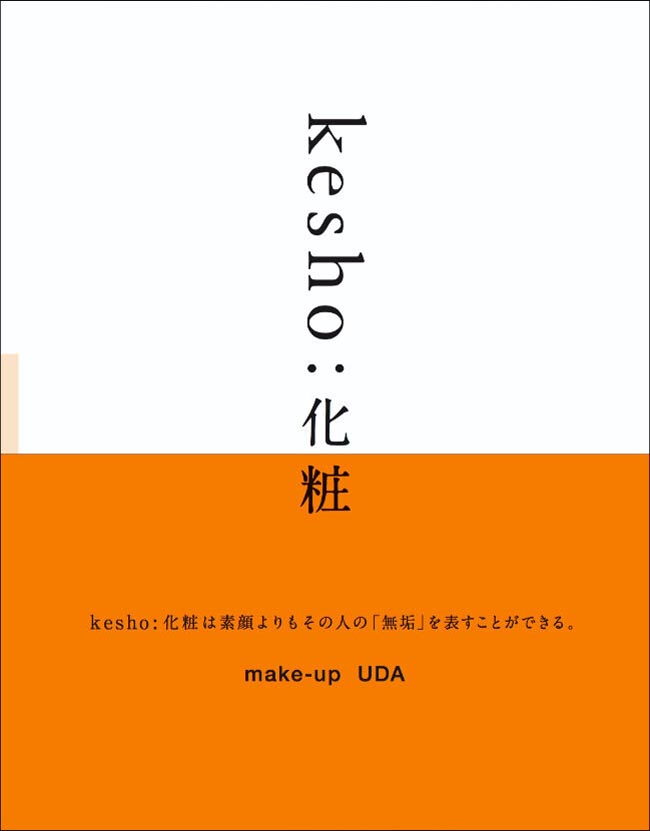
kesho:化粧 著者:UDA、写真:守本勝英、スタイリスト:井伊百合子、ブックデザイン:伊藤修一、発売日:2021年4月29日、体裁:ハードカバー・B5変形版・368p、出版元:NORMAL 詳細・販売:https://mekashiproject.stores.jp/
アンディ・小野・東浦:おおっ(拍手)!
坂田:本の話も後ほど伺わせてください。東浦さんお願いします。
 東浦真弓さん。
東浦真弓さん。
東浦:はい。私は「ブランディング・コンポーザー」と言っているのですが、この肩書き自体を自分で作っているので「何の仕事をしていますか?」と聞かれたら「美容と健康に関して色々プロデュースをしています」と、お応えしています。
かつて雑誌の「マリ・クレール」があった頃、編集部員としてアンディやUDAさんと仕事をしていました。そこから独立して広告制作やカタログ制作などのクリエイティブワークをする一方、長年ビューティ・エディターとして取材してきた情報を生かすべく、リアルメディアとして「パーソナルトレーニングスタジオ」を運営して“美と健康”の情報を発信しています。
坂田:出版社にいらしたのですね。
東浦:そうなんです。創刊やリニューアルが好きで、会社はいくつか変わっていますが、20数年、出版社一筋。最後はアシェット(現在はハースト婦人画報社)にいました。よろしくお願いいたします。
小野:資生堂のクリエイティブディレクターをしています小野と申します。私は大学を卒業してすぐに資生堂に入りました。昔でいう“宣伝部”ですね。グラフィックデザインを担当していましたが、その後はCMプランナー兼アートディレクター的な仕事をして、ここ15年はクリエイティブディレクターとして仕事をしています。
 小野 健さん。
小野 健さん。
学生時代から“女性美の追求”が自分の中のテーマとしてあって、30年以上ずっとそのテーマを追求してきました。
最近の具体的な仕事は主に“エリクシール”とか“アネッサ”等のクリエイティブディレクションをしてきました。
アンディ:フォトグラファーのアンディ・チャオです。出身はシンガポールです。日本に来て21年経ちます。広告や雑誌、写真集など、人を撮る仕事を幅広くやってます。コツコツと努力をしながら、やっと!今日来て頂いた皆さん全員と仕事をさせてもらえるようになりました。
 アンディ・チャオさん。
アンディ・チャオさん。
― 変化し続ける「ビューティ表現」と「美しい」という感覚
アンディ:僕は日本文化も歴史も知らずに海外からやってきました。日本で仕事をする中で「日本人の美学」って素敵だなと。過去の歴史やバックグラウンドがあって、今もクオリティの高いモノを作っている。その末端に自分も参加して、ビューティに関して一緒にものづくりができて最高だと思っています。
UDA:なぜ日本だったの?
アンディ:2000年頃、美やクリエイティブの表現で、日本はアジアの中で一番素晴らしいと思っていたから。日本の音楽にも憧れていました。あと禅や日本庭園、お寺の空間の美とか。ビューティや写真表現に限らず、日本の伝統美に憧れていたんだと思う。
坂田:そういう意味では、資生堂は1960年頃からポスター自体が広告、ビューティ表現の歴史になっていますよね。
小野:昔は時代もあったのでしょうが、コスメのクリエイターはほとんどが男性でした。今年の2月まで展覧会をされていた石岡瑛子さんなどはすごく稀な例で、当時の男性社会に食い込んでいかれた人で、珍しいケースです。
コスメの広告も表現は男が作っていたわけで、「男性が考える女性の美」は1960〜90年代まで続いていたように思います。「男女雇用機会均等法」が1986年に施行され、その辺りから女性のクリエイターが増えていって、表現が広がっていきました。
東浦:その時代のど真ん中にいたビューティオタクが私です(笑)。出版社には普通の編集者として入りましたが、もともと美容が好きで、85年のディオールのポワゾン日本上陸の際に、丸井渋谷店の前で「ポワゾンいかがですか?」と販売していた女子大生が私で「ポワゾンを纏ういい女になるんだ!」と、思っていました(笑)。
女性のメイクアップの進化は、セルジュ・ルタンスなくして語れないですね。70年代にディオールのメイクラインのカラークリエイトを手がけ、その後、資生堂「インウイ」のクリエイターに就任。そのアーティスティックなメイク表現は女性美のリスペクトに溢れていました。それを継いだ2代目クリエイター、ケヴィン・オークインは、インウイの世界観を実用にし、ブラウンのアイシャドー、黒白の陰影美など、商品とテクニックで女性たちを虜にしました。私もまさにその一人。
それまでの「メイクは男へのアピール」という世界から「自分が心地よいもの」という考え方をバンって突きつけられ、本当に衝撃でした。

その後90年代になると「スーパーモデル」が出てきて、ナチュラル・ポジティブな彼女たちは「自分が好き」「私のメイクが好き」という“自分が心地よく思うスタイル”をどんどん発信していきました。その背中を押していたのが、ケヴィンだったかと。資生堂さんは「インウイ」のブランドをはじめ、海外のクリエイティブな風を上手に取り入れていて、日本制作と海外クリエイティブを両輪として、広告表現でも美容業界を牽引していたと思います。
2000年頃はヴォーグ・ジャパンの編集者でしたが、当時の「インウイ」は3代目ディック・ページがプロデュースされていたのですが、長年の「インウイ」愛が引き寄せたのか、私は彼にメイクされるという至福の機会を得たんです!
UDA:「INOUI ID」のパレットですね。
東浦:そうです!! ディックは当時の私に、ピンクのアイシャドウを塗ったんです。「なぜピンク?」と聞いたら「仕事している君じゃなく、君の中のママを表現したかったんだ」と言われて、感動の嬉し泣き! まさに、メイクはIDと体感した瞬間でした。
UDA:スーパーモデルが出てきた頃から、いわゆるdiva(ディーバ)と呼ばれる女性の方が男性よりも強いというイメージが出てきた。男の人が作る理想の女性像ではなく、女性としてのパーフェクトな存在が注目されていました。音楽で言えばマドンナとか、男の人も従えるdivaみたいな。そういう感じが90年代に伸びていきましたね。
坂田:ナオミ・キャンベルの人気は日本でも凄かった。
UDA:そうそう。
アンディ:僕が日本に来る前の知らない時代(笑)。日本に来たのが2000年だからそれまでは学校へ通ったり、世界を旅してたからね。
UDA:アンディの来日前あたりに、ぶわ〜とギャル文化が広まったんじゃないかな。109とかも流行って、すごいパワーのある時代だった。
東浦:2000年頃はコギャルとか小悪魔的なものもあって。
坂田:男性を意識していたメイクから“自分の生き方を主張する”方向に広がっていったのですね。
東浦:ある意味「メイクという表現」によって今までにはない自由を得たんじゃないかな。ガングロメイクとかは、メイクの面白さにアーティスティックな表現を求めて、自分たちの顔をキャンバスにしていった若者がいたわけです。
アンディ:ガングロは一つの民族だと思ってたよ(笑)。
― 1999年に創刊された「VOGUE NIPPON」
東浦:1999年に「VOGUE NIPPON」が創刊された際、私はビューティ・エディターとして、私が憧れたケヴィン・オークインのメイクや彼のメソッドを取り上げる一方で、自由に自分の顔をキャンバスにして育ってきた若者たちにフォーカスしたんですが、VOGUE日本版として、海外のクリエイターやエディターたちに後者が大ヒット。「ガングロメイクのモデルを取材させてほしい」という依頼が多数ありました。日本は島国で自分たち独自の文化を作っているユニークな国なんだな、と自国を客観視できた良き経験。あの頃が、今に繋がる日本のメイク表現の多様化が始まった時代かもしれません。
UDA:今よりもよっぽどオリジナリティがあったよ。
アンディ:UDAさんはもともと化粧品の会社に勤めていたわけじゃないですか。その頃の話も教えてほしいです。
UDA:僕はジバンシイで働いていました。ヨーロッパの会社だから、割とクラシックなスタイルで、80年代の香りがするようなビューティを作っていて。でもデザイナーがジョン・ガリアーノになった90年代後半からガラっと変わっていきました。
洋服で言うと、ジバンシイはカチッとしていてショーとかでも「シワとか絶対作っちゃいけない」みたいな風潮だったのが、ガリアーノになって「シワがいいんだ」という解釈に変わってゆるいスーツになったり。でもマニッシュなパンツスーツとかでモデルが颯爽と歩いてくるのがめちゃくちゃカッコよかった。

アンディ:フリーのメイクアップアーティストになろうと思ったきっかけは?
UDA:当時のジバンシイはジョン・ガリアーノやアレキサンダー・マックイーンのような強い女の人を打ち出すデザイナーがいて、その世界観はすごく好きで、それをメイクという部分で一緒に表現できたらいいなと思っていました。ただ時代の変化もあって、会社の中で自分が表現しきれない部分があって。
小野:商品開発をしていたんですか。
UDA:いえ、商品開発はフランスでしていました。僕たちはパリから来るものを日本人に合うように再解釈したものを打ち出したり、ジバンシイの世界観を日本で魅力的に伝える方法を考えていました。
けっこう色々跨いで仕事をしていたんです。営業やマーケティング、PRから教育からやっていたのですが中々やりきれなくなってきて、“自分の考える女性像”をカタチにするにはフリーになって一つ一つ作っていくしかないのかなと。
社員だった頃は美容部員もしていましたし、地方を回ったり、1日15人メイクをしてそれを20日間すればけっこうな人数になります。それがベースになって雑誌「GINZA」の連載で、一般の人を街でハント&メイクして誌面に出て頂く、という連載も8年ほどしていました。
ジバンシイはファッションブランドだから、デザイナーが変わると世界観も変わる。それに連れてメイクもガラッと変わる。ブランドの名前はあってもね。そういう中でフリーになって18年経ちます。
坂田:一般の方とモデルをメイクする違いはありますか。
UDA:自分の中では変わらないです。表現の技術という意味ではプロとしてショーに出るモデルや、演技で表現する俳優という仕事をされている方との違いはあるかもしれないけど、一人の女性として考えると、内面的には何も変わらないです。
メイクに関しては、プロのモデルが起用されることが多いですが、顔のカタチ云々となると、そこで話が止まるというか、全部テクニックの話になる。本当はビューティって、内面の話がすごく大きいんです。一人一人の“個性”とか“らしさ”、その人の世界がどこに表れるのかって言う話になると、一般の人であろうがモデル、女優であろうがまったく一緒なんです。
店舗で一般の女性にメイクをする時も、色々な話をする中で養われた感覚はあります。美容師に近い感覚もあるし、スタジオワークもやったのでそこは経験値がうまい具合に自分の中でブレンドされていった感じですね。
アンディ:僕は3人とも仕事をしているけど、今のUDAさんが内面を重視しているという話を聞いて、一般の人に商品を買ってもらう小野さんにも近い印象を受けました。クリエイティブディレクターとして、意識していることは何ですか。

小野:僕の場合は、資生堂の社員として広告を作っているので、会社の売り上げとか、ブランディングを考慮しつつ、割と限られた世界で作っているのかもしれない。
主に女性向けの商品を担当している中で、ターゲットに共感されないといけません。マーケティングではインサイトを探ってどのようにしたらその人たちが共感してくれるのか探っていきます。
起用した女性の計算された美しさ、例えば経験値とかその人の才能の中から出てくる表情は素晴らしいのだけど、それに加えて「その人は、本当はそこを見せたくないのでは」という部分がチラッと見えちゃう、その人の本能の部分とか感情、欲望とか、それがちょっと見えた時に人の気持ちって動くんです。
それは冷静な人ほど見せないようにしているし、最近はクールでカッコよく振る舞える人は増えているけれど、ちょっと隙を見せた時に出てくる“本能が出た瞬間”を意識してアンディとも写真や映像を作っています。見ている人は、それがどこかわからないかもしれないけど、心が動かされるのはそういう瞬間だったりする。

SHISEIDO ANESSA(2017)CD/Dir:Takeshi Ono Ca:ND CHOW
東浦:そう思いますね。
小野:現場でくだらない話もしながら、その隙間が見えるチャンスを狙っている部分もありますね(笑)。例えば「カット」って言った後に、その人がふと“素に戻る瞬間”がめちゃくちゃステキだったり。
UDA:アンディもそうだけど、メイク直しをしている時に「そのまま!」って撮る人もいます。例えばリップを塗られている時って素でいたりするじゃないですか。その時に“無意識の美”を感じるんじゃないかな。
アンディ:一緒に仕事をした人は知っていると思うけど、僕の場合は撮影の時に被写体を笑わせたり、敢えて不意をつくように話しかけたりして、混乱させるんです。
いつも被写体を混乱させて“見せてくれない一面”を引き出せるか“1秒の美”だったり“香り” “目線”“唇のしぐさ(形)”とかで「あっ」と思った瞬間に撮影しています。
決まった絵を撮る時も、それはちゃんとやるんだけど(笑)、撮影時はそれとは真逆の表情を狙っていたりする。僕は言葉で提案するよりもビジュアルで見せる派です。

坂田:モデルも女優も、プロとしての魅せ方を自分でよく知っていますよね。なので敢えてそこを外していく感じ?
アンディ:そうそう。僕、人のコンプレックスを意識しています。被写体の人に「コンプレックスはどこですか?」と直接聞くこともある。例えば「お尻が大きいのがイヤ」と言われたら、お尻ばっかり見る(笑)。お尻に限らず手や体のパーツで、そこが美しいと感じた時にシャッターを切る。それを見せると、撮られた人が「あれっ?」ってなる。「コンプレックス」と思っていたところが、逆に魅力的に見えることがあるんです。
UDA:基本的にはそこが一番の良さだったりしますよね。
小野:フードの場合“シズル”って言うじゃないですか。美味しそうとか、瑞々しいとか。コンプレックスって、人間でいう“シズル”なんじゃないかな。
広告表現はマーケティングの一環だから、丸いものしか作りづらいじゃないですか。色々機能を謳わないといけないとかね。それを言い続けて15秒間作るわけだけど、その中にちょっとシズルを入れてあげると良くなるんです。
UDA:視聴者は、説明部分はそんなに重要視していないじゃないですか。それは企業側が伝えたいことであって。でも今おっしゃっていたように「魅力的に見えるかどうか」に反応する気がします。
小野:それが一瞬でも入っていると、意外とベタな言葉もよく聞こえてきたりしますよね。

SHISEIDO ANESSA(CD:Takeshi Ono PHOTO:ND CHOW)
アンディ:広告制作では、コピーが先か、ビジュアルが先かってあるじゃないですか。どちらが先でもフレキシブルにできればいいよね。
UDA:本当は素敵な絵を想像できる為のよいコピーばっかりがあればいいですけどね。ただその企業や商品の“事情”みたいなことがコピーになっていると、なんかしっくり来ないことも起こり得るなあ。できるだけ“シンプルな状態の美”が撮れたら、伝わるのにと最近思う。
アンディ:写真って“永遠に魅力的な写真”と“旧くなる写真”があるじゃないですか。永遠の写真は、その時代のブランドのイメージと登場した人物の心境(シズル)が入っていると、いつ見ても魅力的な写真になる。資生堂だったら前田美波里さんとか、山口小夜子さんから始まっている。
最近のビューティは雑誌でも広告でも情報ばっかり詰め込んで終わってしまうものが多い。だからプレゼン用のラフを作ったりイメージを共有する際に、昔の広告や、雑誌のキリヌキが参考資料として出てくる(笑)。
UDAさんは「メイクするために究極的には顔は要らない」って言っていたんです。つまり雰囲気が大事だと。
UDA:さっきの瞬間の話じゃないけど“ムード”っていうか。メイクのことは伝えたい部分ではあるけれど、大事なことはメイクそのものよりも“メイクされた人が醸し出すムード“のためなんです。メイクが目立ったら僕の中では少し違ってしまう。だからアンディもそうだけど“表情を切り取るフォトグラファー”じゃないと僕は合わないこともたまにあります。
アンディ:メイクの人も、毎回同じように仕上げる人もいるよね。自分のメイクを見せたい、自分のグラデーションを見せたい、というタイプ。そのメイクの人が好きなリップの色を(他の仕事でも)多用するとか。
UDA:それもわかるのだけど、それもメイクをする相手のムードのためであって欲しい。
小野:その人が一番魅力的に見えることが大事だよね。
UDA:そうなんです。メイクはその人がパッと見た時には見えていない魅力を引き出すスイッチになっていればいいのだけど、そうなっていなければメイクをしてもしなくてもいいような…。
アンディ:極端な話、UDAさんとの仕事ではノーメイクで出てくる時もある(笑)。「えっ、もうできたの?」ってなるけど、実はメイクされているんです。
UDA:空間に光と影があって、その人が本来持っているものを通して表現したいムードが出ていれば、何もしなくてもいい場合もありますよ。
小野:やればやるほど、ダメな人もいますね(苦笑)。
UDA:います。それはたぶんムードを見ていないで“メイクのことだけ”だからなんでしょうね。
小野:技術はしっかりしていて、きれいに塗ってあるけれど、やればやるほど可愛くないという…。
アンディ:顔がメイク情報になっちゃうですよ。僕は写真を撮っている時に色々なことを考えているのだけど、UDAさんはメイク中に何を考えているんですか?
UDA:場合によりますけど、そのテーマに対して被写体の人がどう見えればいいのか、というのがあって、それに向かうにあたって“この人はどういう人なのか”を会話しながら考えます。
例えばテーマが「強さ」だったら、その強さがこの人のどこにあるのか。“根底の意思の強さ”なのか“攻撃的な強さ”なのか、色々あると思うんです。そことあった強さを目指さないとずれちゃうし、ただメイクしているだけになってしまう。そこは一番気にするところですね。
坂田:東浦さんはどういう視点で、モデルやメイクを見られていましたか?
東浦:私がモード誌に携わっていたのはモデルが好き過ぎるというか。いつも時代の女性像を考えていましたね。キャットウォークを歩いているモデルたちを見て「この娘好きだな〜」とか「この娘とこのブランドは相思相愛」なんて思いながら、時代の空気感をチェックしていましたね。
ヴォーグとマリ・クレールは読者が違います。その媒体に合った女性像にして時代表現するということを楽しみながら作っていましたね。タレントさんでも「あのタレントにこの服を着せて、こんな写真撮ったら話題になるんじゃないか」とか。
UDAさんの話を聞いていて、そういえば私も、著名な女優をキャスティングした時、その人のイメージされる姿で写真を撮ろうと思ったことは一度もないなと。その人がやったことのない事をどうやってやろうかっていつも考えていましたね。
UDA:それって東浦さんがその人の中に“これじゃない何か”を感じていたからなんでしょうね。
東浦:そうかもしれない。女性同士だからできる会話もあるし、オーディションでこっそりボディラインを見せてもらいながらトークすると、新しい一面が見えてきたりする。そうすると、この服がいいとか、このモデルなら鎖骨を見せた方が魅力的に見えるとか。でも本人はそこにホクロがあったりそばかすがあると見せたくないんですね。でもそこがよかったりしたので、コンプレックスや内面の話と同じだなあと思いました。
それと同時にコンプレックスを持つ気持ちもわかるから、事前に丁寧に説明をしたり、しっかりした企画書を作って説得したり、安心してもらうような撮影の仕方はしていました。だからこそ、女性像を作る時にヘアメイクの感性は重要ですね。

ブランドが19世紀にフランスに自在した「メルヴェイユーズ」という時代を先取りした女性たちであることから、常にこのブランドの広告は、普遍性と時代感を追求し制作。 @2016 Les Merveilleuses LADURÉ
VISUAL DIRECTION & MAKE UP:UDA Photo(Model):ND CHOW CD:Mayumi Toura
ある時代にすごく人気のあったメイクアップアーティストっているじゃないですか。それも一つの歴史ですが、UDAさんのように一人一人を見ていく方が長く制作の現場を続けていけると思います。その人らしさを突き詰めると同時にトレンドを意識した「今描くビューティ」が必要なのも事実。いつも目的を持ってチームで動いているので、現場でセレクトする際に「これいいね!」って選ぶカットは、スタッフも大体同じ意見なんですよ(笑)。
アンディ:同じ写真を選ぶよね。100枚見たあとに「やっぱりこれかな」って戻る(笑)。
東浦:それを見て下さった方が共感してくれれば、広告であれば“結果を出す”ということに繋がるんじゃないかな。エディトリアルの場合は、その雑誌に読者がついているので、そのファンに“自分たちが良いと思うもの”を発信できたというのは、特権だったかもしれません。
アンディ:小野さんは何を考えてプランニングされていますか。小野さんのすごいところはCMの音楽もかなりこだわっているところかなと思います。
小野:音楽はビューティには直接は関係ないんだけどね(笑)。
東浦:でも時代を反映しているので大事ですよ。
アンディ:小野さんはCMソングを作詞するんですよ。
坂田:おおっ、作詞家ですね。
小野:プランニングの一環なんです。ナレーターが語るよりも「音楽の中にメッセージを入れた方が届くだろうな」という時はそれを歌ってもらいます。もちろんミュージシャンとの擦り合わせもあるのだけど、結果的に何本かは作詞したことになっていますね。
企画を伝えるために必要なものは何でも利用するし手を抜かない。テレビCMは15〜30秒で語らないといけないので、時には20カット以上入れる場合もあります。でもその内の0.5秒とか、1秒しか使わないカットにものすごくお金をかけていたり…。
坂田:一瞬でも大事なシーンならばお金を使う意味がある、ということですね。
UDA:CMの尺でも、昔はストーリーに惹きつけられるものがけっこうあったわけですが、特にここ数年で時代が変わって、商品説明がバンと出たり、その時旬なタレントが何か言ってたり、じっくり作るCMが減っている気がするんです。
ただコロナ禍で人の移動が制限されたり、ステイホームする中で自分と向き合った人も多く、そうすると、やはり心に響くものを求めるようになっている気がして…。そんなことが背景にあるからなのか、「ちゃんと伝わるものを作ろう」という機運が出てきているじゃないかなと。自分もそういう現場に携わらせてもらう機会が、以前よりも少し増えてきていると感じます。
小野:情緒的なものが出てきているのかも。マーケッターの人たちの感覚がコロナ禍で変わってきているのかもしれない。クリエイターは常にいいモノを作りたいという思いはあるけれど、厳しい日常が続く中で、情緒的なものを求める人が増えているのだと思います。
UDA:だとすればすごく嬉しいですね。さっき話していたムード的な部分がより重要視されていくといいな。逆にマーケティングって意味あるんでしょうか。
小野:言いたいことはわかります。マーケティングって、全て過去の調査に基づくものですからね。
UDA:自分の好きなものはすぐにインスタにアップして、やりたいことを発信する人がどんどん出てきている“秒速の時代”に、過去を追うだけでは分かり得ない時代になりかねない。
東浦:今はネットで調べて、欲しいものだけを選別する目の肥えた時代になっているよね。
UDA:だとしたら、いかに“その商品が魅力的に見えるか”という努力をしないと。
東浦:エモいとか、心に響くものしか要らないというね。

Dr.Recella「ADS」(CD:Mayumi Toura)
小野:CMの媒体料って今でもそれなりに高い中で、徐々にWebでのプロモーションが主流になってきているじゃないですか。現状ではまだCMに比べたら安いので、企業はそこにお金を投資して、1〜2分の動画も作れる。それもあって情緒的なものを含めたコンセプトムービーが増えている理由かもしれない。
坂田:今の時代「共感」というキーワードがないと、企業からの一方的なメッセ―ジは響かないですね。
小野:そのためにも15秒では収まらない映像表現はこれから益々増えるでしょうね。ただCMの世界もそうなるといいなと僕は思っていますけど。
東浦:いまCM(テレビ)をリアルタイムで見ている若者って少ない気がします。企業もCMを一切打たないわけにもいかない事情もあるでしょうが、メディアが広がって制作者側からしても表現の場が増えているじゃないですか。コロナ禍で家にいる状況でも、テレビじゃなくてネットを見るわけです。コロナが治まってきたとしてもテレビに戻るわけではなく、むしろよりネット視聴は増えていく中で、企業広告やメッセージの出し方は変わっていくでしょうね。
坂田:企業から押しの強い情報はスルーされがちですよね。単に商品を買う時代から企業理念、企業哲学に共感して商品を選ぶ時代になってきている。ファッションでもサステナビリティが重要視されていますしね。

坂田大作(SHOOTING編集長)
小野:今はネットで情報収集が容易になっていますからね。本当は最先端でいたはずのCMが、逆にいまは少し遅れているのかもしれない。それとしっかりとした理念のある企業のCMが減って、CMの質が低下している気がしますね(苦笑)。
ただそれが落ち着いて、CMにもいい流れがくるように自分達もしていかないといけないし、ネットとCMのどちらがいいという選択ではなく、媒体ごとに表現を使い分けられればいいですね。
坂田:コロナ禍で外出自粛が叫ばれ、また企業のリモートワークが進む中、女性の見え方、見せ方に変化はあるんでしょうか。
東浦:各社リップが売れないという話は聞きますよね。
小野:企業側の視点で言うと、コロナ禍で化粧品の売り上げはかなり下がっています。外出の頻度が減って、自宅ではあまりメイクしないし。
外出時はマスクをしているのでメイクは目元だけですよね、だからみんなキレイに見えます(笑)。
UDA:目が魅力的かどうか、って大事ですね。
アンディ:フォトグラファーも目を見ちゃう。
UDA:絶対目を見て話すし、お化粧をする時も目の見え方をすごく意識します。顔の中で目がいい見え方をする、というバランスの取り方をしますね。
ー LGBTやジェンダーレスとメイクの関係性
坂田:日本でもLGBTやジェンダーレスがようやく認知されつつあります。そことメイクの見せ方や販売方法などで変化はあるんでしょうか。
東浦:男性が女性化できるアプリがすごく流行っていて、中年男性でもハマっている人がいて、
「自分がどれだけキレイになれるか」をSNSに上げたり、いわゆる承認欲求が強い方が増えている。化粧品も女性用、男性用化粧品と謳うのはやめましょう、となってきています。
UDA:僕は元々そういう考え方です。男性女性ではなく“人”なんだよね。
東浦:メイク用品は男性も使いますからね。
UDA:「メンズ用のメイク商品」ってありましたが、メンズ用ってどういう事なんだろうって(笑)。「メンズって言っても目があって鼻と口があって同じじゃん」というのを少しだけ感じました。
東浦:うちの若いスタッフがある広告(モデル)を見ていて「かわいい!」って言うから覗いたら自分は「えっ」という感じ。つまり若者の「かわいい=好き」なんだなと。男も女も「かわいい」という単語を使います。私の感覚では「クール」「素敵」なものでも「かわいい」となる。
アンディ:ボキャブラリーが少ないんだよね。
UDA:自分が中高生だったのは30年以上前で、今とは違うんだろうなと思います。今は男の子でも母親とも普通に買い物に行ったり、女の子とでも男女の意識なく友達として付き合っている人も多い。だから言語も共通してくるんじゃないかな。
東浦:男性でもメイクをしてみようというのは、普通になってきていますね。

ettusais「puru puru serum」(Photo:ND CHOW Make up:UDA Model:Sam.S)
アンディ:言逆に女性をカッコよく、マニッシュにしていく方向もあるよね。UDAさんが男性をメイクする時に何か違いはあるんですか。
UDA:基本は一緒です。「普通の会社員の人にメイクしてください」と頼まれたらどうするか戸惑います。メイクすることは、自分の世界を出すというか“自分の内面と外見の調整”と思っているから。女性的色気を求めていたら、それに合わせたメイクを成立させることはできます。
あるいはメンズモデルの撮影で、見た目がワイルドな人だけど、少し繊細な人にしたいというオーオーダーがきたら、それはわかるんです。顔のクセを抜いていくとかね。男性で単に肌をメイクできれいに見せたいとかは、微妙にわかんないなあ(笑)。
アンディ:ある仕事で女装家を撮る時にCDに聞いたことは、「この人を“女装している男性”として見せたいのか、“完全に女性として撮る”のか、それが決まらないと僕は撮れません」って、話したことがあります。UDAさんとも仕事で同じようなことをやったよね。
UDA:年齢がいった、今までメイクなんてした事もない普通の男性だったけれど、その人をdivaみたいに完璧に化粧をする企画でした。最初は難しいなと思ったけれど、バッチリ化粧をしたら、そしたら彼の中でほんの少し、何かが開いたんでしょうね。僕らも女性として接したんです。そしたら最後は、女性っぽい振る舞いになっていった。
アンディ:撮影が終わってもそのままいたよね。
UDA:女装とかにまったく経験も興味もない人が、すごいフェミニンになってて驚いたよ。
東浦:おそらくどんな人の中にも、異性的要素があるんでしょうね。
アンディ:たぶんその時のスタッフがみんな男だったから、女性のように変身させられたのかも。
小野:「キレイだな」って思う瞬間ってあったの?
UDA:少しだけ。素はただのオジサンですからね。でも撮っていて後半だんだん色っぽくというか、愛おしく思える瞬間があったんです。
アンディ:だから結局“ビューティは本能”ですね(笑)。
東浦:「ビューティ=人間らしさ」なのかな。
アンディ:撮影している中で人の変化が好きなんです。肌の艶も変わってくるし。撮り始めと最後の方ではすごい変化するんですよ。熱くなってくるとリップもチークも色が変わってくる。肌も湿度を帯びて艶が出てきたり…。メイクされた後でも、時間と空間でそれが変化していくのが面白いなあって思う。
ー 2021年半ばですが、今考えていることや今後やってみたことがあれば教えてください。
UDA:今回「kesho:化粧」という本を出版した理由を話します。先ほどの話と繋がるんですけど「自分らしいメイク」とは何かと問われた時に、メイク本では「あなたは目が大きいからこうした方がいい」とか、だいたい形態から来る話がほとんど。鼻は高いから丸いからこうした方がいいとか…。それはガワの話であって、本来「自分らしいメイクをする」という話は「内面をどう出せるか」という話だと思っています。同じ赤でも「鮮やかな赤が好き」という人もいれば「深みのある赤が好き」という人もいます。人によって、その日の気分によっても変わるわけです。それって内面の話なんですね。

kesho:化粧「牡丹華」

kesho:化粧「温風至」
基本的にいままでは「メイク=洋式美」なんです。「こうすると可愛く見える」それをHow To化して「こうすればキレイになれますよ」という話。この本の内容は、やり方ではなくて、考え方・捉え方、なんです。雑誌の連載「美人化計画」という企画でも、それぞれの人と話して、その人の中にあるもの、例えば「映画のこういうシーンが好き」とか「自分はこんな色の服が好きだ」とか、その人の話を聞いて、イメージが湧いてきた時に「こんなメイクがいいんじゃないか」という表の作業になるんです。
それって100人いたら100通り、その日の気分も入れたら無限に広がっていくので、僕のやり方を教えるのは無理なんですね。手を動かす前にまずそこを探すのが重要じゃないかと思っています。
そしてコロナ禍でいやがおうにも自分に向き合う時間が増えた時に、日本人とか四季とか、アンディだったらシンガポールのことを思うだろうし、それぞれが自分らしさを考えたときにもっと自分の感性を大切にしたいなと。そうなるとにほんじんとして“季節”をもう少し感じてみたいなと。例えばこの季節に様々な色の花が咲いているけれど、黄色の花に反応した人がいたら、顔のこの部分にあの黄色を付けてみようってなるのが、本当のオリジナルだと思うんです。
そういう感覚で“自分の無垢な部分”を素直に表すことは、西欧の真似でもクラシックな和装の化粧でもない。それを日本の四季、二十四節気をさらに約5日ずつの3つに分けた「七十二候」に沿って化粧を考えて作ったものをまとめています。
アンディ:和菓子と感覚が似てるよね。
UDA:そう。日本のメイクも進化しているのだけど、どこかで「立体的じゃないと」とか「小顔に見せたい」とか、完全に西洋の美意識なんです。それよりも季節で変化する和菓子のように、日本人や東洋人は平面的な顔ですが、それに合わせたやり方とそのときの気分がポンとのったら、その人らしさが出てくる。
「スイーツは自分が食べたいもの」「和菓子は人をもてなす際に自分の感性をフルに使ってお出しするもの」とある京都の知り合いから伺った際に「日本人の化粧にはその要素があるかもしれない」と、その話を聞いてしっくりきた。ただ「七十二候」(72点)作るのはけっこう大変だったけれど。
小野:「おもてなし」の精神がありますね。「相手にとって心地よい」みたいな。
坂田:東浦さんはいかがですか。
東浦:私は制作の仕事をしながら、現在はトレーニングスタジオの運営もやっています。
姉がフィジカルトレーナーをしていて、40代半ばに、怠けていたツケで絶望的に崩れている私のボディラインを見た彼女が、「女性美を追求している人としてどうなの?」って何気なく言ったんです。それがきっかけで、改めて自分と向き合うというか、「私って何者?」と自分の「素」を考えあるべき私の姿へといろんなものを削ぎ落としたいな、と思ったんです。いわゆる肉体改造ですよね。
すると、顔も上がったり、ウエストがここまで細くなるんだとか、あっ今はほっといてくださいね(笑)。見た目だけじゃなく心も軽くなって、意外と欲しいものがミニマムになるんです。食事もそうですが、体を健康に保つことで肌のコンディションもよくなります。ファンデーションを塗らなくても済むように保てば、逆に“ここぞ”という時のメイクが楽しいとか。トレーニングの実践で維持する自分美があれば、実は人は強くなれるんじゃないかな、と思って、リアルメディアとして、トレーニングスタジオを作りました。
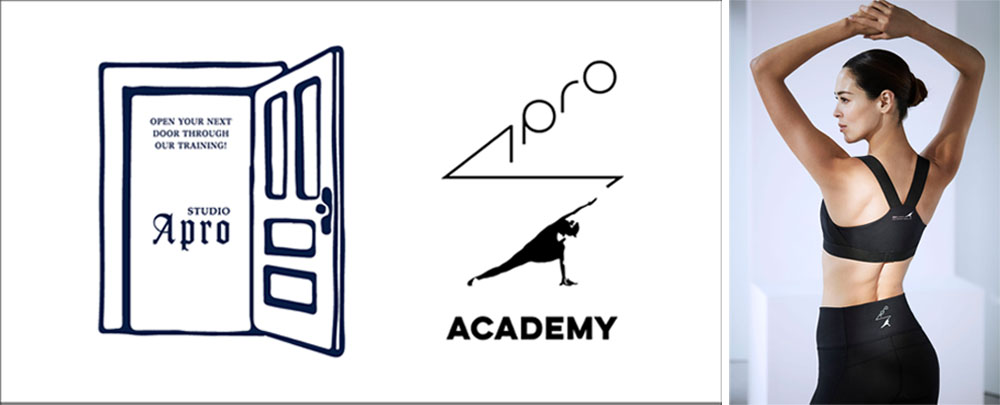
STUDIO Apro/Apro ACADEMY
https://tsapro.co.jp/
20〜30代の若い子でも、身体がほぐれると帰りは笑顔になります。自分の身体を見直す時間を当たり前にすると、結果的に笑顔が増えます。まず自分が幸せでないと表面だけでビューティは成り立たないのかなと。いまは飾る前の“素をよくしていく場”を提供しています。
それは先ほどUDAさんの話ともリンクするのですが、季節による変化とか、冬に冷え性の人はどうすればいいのか、旬の食べ物を摂るのが重要とか、“四季と食”を考えていた昔の日本人ってすごいんだなと。自分を改造することで、本当に欲しいもの、必要な見せ方とかが見えてくるので、いまはその活動にも本腰を入れて、楽しみながら行っています。
小野:広告の仕事をしている身としては、先ほど話に出たような「本能」に少しでも響くようなものを作っていきたいなと思っています。
昔、「仕事は全て社会貢献のためにある」とある人に言われて「自分がどんな社会貢献ができるんだろう」と考えた時期がありました。その時ちょうど少子化の危惧が叫ばれ始めた時期だったから、「僕の作ったもので少子化をなくします!」って言ったら笑われたんです。
でも僕が資生堂に入った動機は、70〜80年代の資生堂のCMを見て、こういう車にのって、こんなキレイな人とデートしたいとか、素直に思ったから。そのために勉強しなきゃとか、努力しなきゃと思ったんです。でもそんな風に感じられる広告は今ほとんどないなと。そういうものを作りたいし、自分が作っているものでちょっとでも感じて恋をしたりとか、がんばって告白したり、キレイになろうと思ったり…。それはゆくゆくは少子化を防ぐという(笑)、それくらい響くもの作っていきたい。

SHISEIDO ANESSA(2018)CD/Dir:Takeshi Ono Ca:ND CHOW
デジタル化、ダイバーシテイ、ジェンダーフリーとか、個性を大事にする時代になって、アプローチする幅も広くなってはいるものの、本能の部分は今も昔も変わらないんじゃないかなと思っているので、広告やCMという世界で少しでも“本能をくすぐるもの”を作り続けたいなと思っています。
アンディ:僕が写真を撮っているのは、昔から人に興味があるからなんです。何を考えているのか、心境とか。いまはデジタルカメラになりさらにそれが進化して、ただのツールになっちゃった。だからこそ、僕が相手のことをわかって、写真を撮ることで、その人のまわりの環境や生き方を全部知ることができたら面白いなと。
色々な人たちを撮影していて、裸にするとか脱がすためじゃなくて、一皮むける、生まれ変わると言う意味で肌を撮ることが大事だったり。タレントでも女優でもモデルでも、「新しくステップアップするきっかけとしてアンディさんに撮ってほしい」というオファーが増えているんです。企業で言うと、新しくスタートするブランドの立ち上がりの仕事が大好き。新しくチェンジしていきたい人や企業を撮ることは楽しいし、やりがいもある。そしてその人が「今考えている心境」のバックグラウンドが見える写真が撮りたいなあと思う。
あと“写真の深み”かな。それは技術じゃなくて、歴史とか哲学とか心理学を含めてビジュアルにどう“深み”を入れていくのか。何かを考えさせられるビジュアルを作れたらいいなと思う。

Photo:ND CHOW
坂田:世の中には、メイクの教則本や写真テクニックのハウツー本はたくさんあるけれど、今日の話では「本能や内面的な部分をどう具現化していくのか、琴線に触れさせるのか」そういう話がとても興味深かったです。
コロナ禍はまだ続きますが、機会があればまたこれからビューティがどう変わっていくのか、またこのメンバーで話ができればと思います。ありがとうございました。
ND CHOW(アンディ・チャオ)(フォトグラファー)

シンガポール生まれ。2年間世界を旅したのち、2000年に東京へ移住。この2年間の経験が今日の写真家としての感性や洞察力へとつながり、美学、哲学が形成された。現在は、多くの広告、ポートレート、写真集等で活動中。
2004年『小澤征爾サイトウ・ キネン・オーケストラ欧州を行く』を出版。ツアーに完全密着したフォト・ドキュメンタリーは、 最初の写真集と言える作品となった。作品はほかに、浜崎あゆみをはじめとするアーティストのアルバムカバーや、トム・ハンクス、北野武、ファレル・ウィリアムス、シンディ・ローパー、パティ・スミスなど世界的な著名人のポートレイト等、多岐にわたっている。日本では、 広告をメインに、エディトリアルでも活動、また数多くの写真集、ミュージシャンのポートレイト撮影も手掛け、2020年 LUMIX Gallery “アンディ チャオ ✕ 綾瀬はるか”の写真展を開催。
https://ndchow.com/
https://www.instagram.com/ndchow75
UDA(メイクアップアーティスト)

大手化粧品会社にてPR、マーケティング、教育、 店頭プロモーションなど様々な業務に携わり、その後独立。現在は、国内外のエディトリアル、コスメティック・ファッション のキャンペーン広告、企業CM、舞台、ドラマなどの多岐に渡るフィールドで活動。
独自のファッション感、ビューティの視点を生かし、日頃から様々な場面での新しいアプローチを試みている。
著書:『kesho:化粧』(NORMAL)
コレクション: UNDERCOVER、JUNYA WATANABE COMME des GARÇONS、Mame Kurogouchi、AURALEEなど。
http://uda-kesho.com
https://www.instagram.com/uda.kesho/
https://www.instagram.com/udashi/
小野 健(Takeshi Ono)(株式会社資生堂 クリエイティブ本部 エグゼクティブクリエイティブディレクター)

武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科を卒業後、1990年にグラフィックデザイナーとして資生堂宣伝部に入社。1994年からアートディレクター兼CMプランナー、2006年よりクリエイティブディレクターとして化粧品ブランドを中心に担当(ティセラ、ピエヌ、プラウディア、ジェレイド、TSUBAKI、エリクシール、アネッサなど)。クリエイティブディレクターの他に、CMディレクターとして数々のCMの演出も担当。ビューティー表現と合わせて音楽タイアップ広告を得意とする。
東浦真弓(Mayumi Toura)
株式会社T’s apro代表/株式会社OUV代表
ブランディング・コンポーザー/プロデューサー/ビューティ・ディレクター/編集者

大学卒業後、出版社勤務。20数年、モード誌から実用誌まで数々の女性誌を手がけてきたベテラン編集者。 2000年『VOGUE』日本版創刊に際しビューティ・エディターとして参画。その後『マリ・クレール』編集長を経て独立。 女性美の追求を使命とし、個、企業、メディア・店舗・商品とジャンルを問わず様々なプロデュースを手がける。時を読み、本質を見抜く着眼点に惹き込まれるクライアントやクリエイターは多い。ポテンシャルを瞬時に捉え、そこからさまざまな才能をマッチングさせ、時代の波に乗る「オンリーワン」のクリエイティブに昇華させることを得意とする。特技は新たな才能を見出すこと。
https://company.tsapro.co.jp/